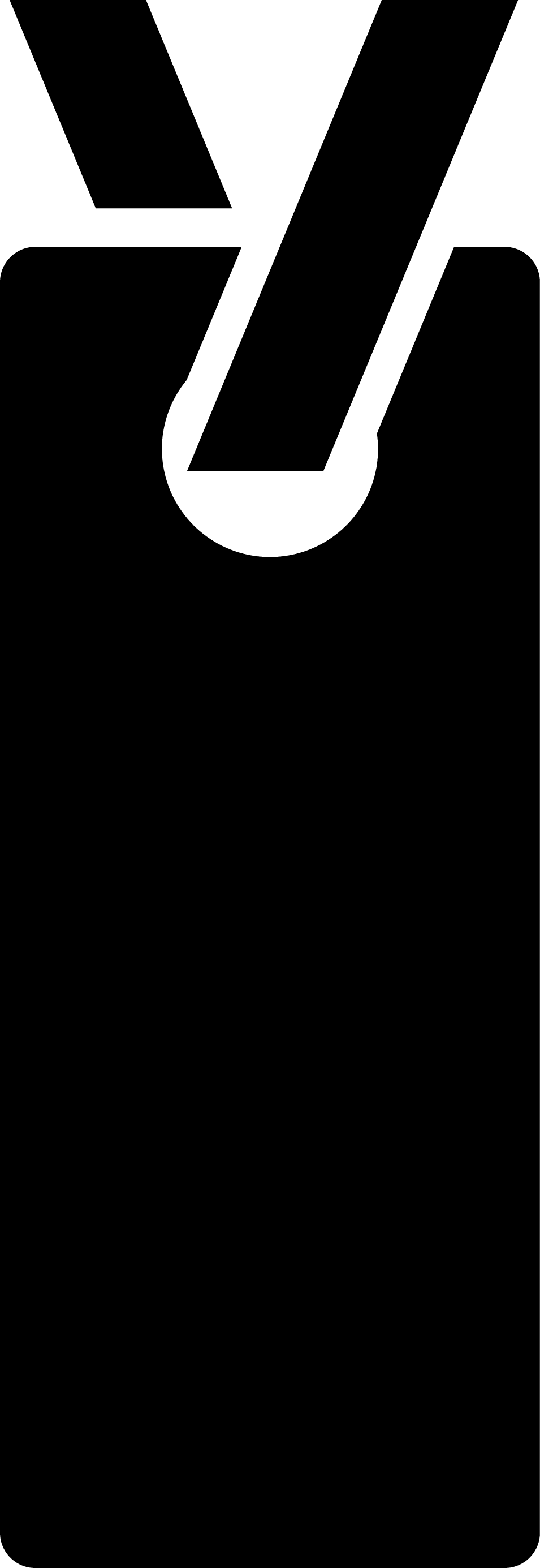

美鈴の部屋
ふんわりとしたムースをフォークで切る感触が心地いい。
口の中に入れれば、じゅわっと広がって溶けていく。
それは、とても幸せな時間だった。
・
・
・

レストラン廊下
 美鈴
美鈴
すごく、すごく美味しかったんだけど!
 美鈴
美鈴
なんていうか、天才?天才なのでは!?
 露衣
露衣
……まあ、みんなからはそう言われてるな。
お店に来て、開口一番に詰め寄れば、当たり前のように露衣さんは認める。
だけど、それにだって頷くしかない。
昨日の帰りに貰ったケーキが、それはもう衝撃を受けるほど美味しかったのだ。
 美鈴
美鈴
あ〜。やっぱり天才よね。そうよね。あんな幸せな味、天才じゃなきゃ出せないよね。
 美鈴
美鈴
昨日の私、すっごく幸せだったもん。
 美鈴
美鈴
ふわあーって気持ちが上がってね! 食べ終わっちゃうのがもったいなくて、もったいなくて……!
 美鈴
美鈴
ほっぺたが落ちるってよく言うけど、頬が緩み過ぎて、本当に落ちちゃうかと思ったよ!
 露衣
露衣
なんだ、それ。
それまで表情を崩さずにいた彼が、ぷっと吹き出す。
 露衣
露衣
その顔、本当に美味かったんだな。
笑うと、端正な顔をした彼が少年のように見えてちょっと可愛い。
そして自分が興奮しすぎて、彼に対して敬語を使うのを忘れていたことに気がついた。
 美鈴
美鈴
うん……。じゃなくて……、はい。興奮してすみません。ありがとうございます。
 露衣
露衣
どーいたしまして。
露衣さんが私の横を通りすぎながら、子供にするように頭を軽くぽんぽんとしてどきりとしてしまう。
 露衣
露衣
まあ、俺の料理だからな。当然の結果だな。

くつくつと笑う露衣さんはやっぱり自慢げで、でもそんな態度が嫌じゃないと思う自分がいた。
・
・
・

レストラン店内
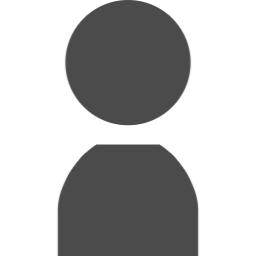 お客様
お客様
えっ。お持ち帰りできないの?だってこの間まで平気だったじゃない。
 美鈴
美鈴
すみません。実は保健所の指導が入りまして……。
あれ以来、私はそう言って折り詰めを断っていた。
残念そうにするお客様は多かったけど……。
 美鈴
美鈴
(でも、露衣さんの話を聞いたら、やっぱりこうするべきだと思う)
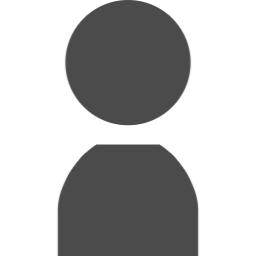 フロアスタッフ
フロアスタッフ
帝塚山さん、よかったの? 断って。
 美鈴
美鈴
うん。だって、やっぱり一番美味しい料理だけを食べて欲しいし。
 美鈴
美鈴
お客様に喜んでもらいたいけど、ここはレストランだから。
 美鈴
美鈴
味よりもサービスを取ってシェフの料理を誤解して欲しくないんだ。
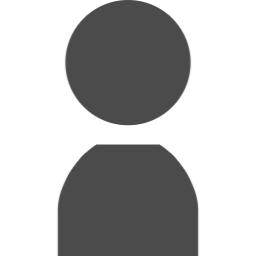 フロアスタッフ
フロアスタッフ
まー確かに、それもそうね。あれだけ極めている料理ならなおさらね。

レストラン廊下
 露衣
露衣
…………。
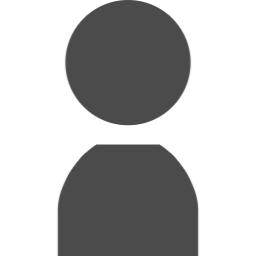 調理スタッフ
調理スタッフ
……露衣さん? どうしたんですか、そんな所で立ち止まって。
 露衣
露衣
あ……。いや。
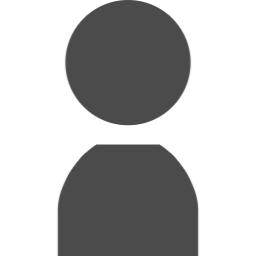 調理スタッフ
調理スタッフ
ん? なんか顔、赤くないですか?熱でも……。
 露衣
露衣
……何でもない。
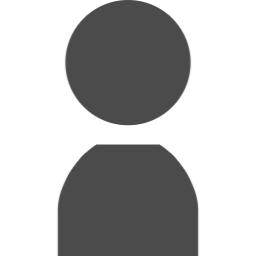 調理スタッフ
調理スタッフ
えっ? ちょっと待ってくださいよ。大丈夫なんですか!
 露衣
露衣
何でもない……!
そんなことがありつつ……少しずつ私達の関係はいいものへと変わっていった。
・
・
・
……だけど、レストランの状況はそうはいかなかった。

レストラン店内
 美鈴
美鈴
えっ! 今日の予約、入ってないの!?
予約台帳を見て愕然とする。
いつもいっぱいだった予約が、驚くほど減っていたのだ。
 美鈴
美鈴
だってこの間、シェフの技術が高いって雑誌に特集されたばっかりなのに……。
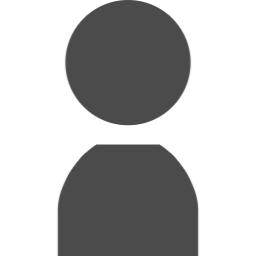 フロアスタッフ
フロアスタッフ
うん……。そのお陰で土日は入ってるけど、平日は……もう全然よね。
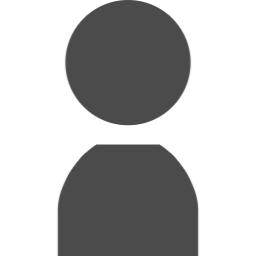 フロアスタッフ
フロアスタッフ
あーあ。最近はお客様からもいい声が聞こえなくなってきたし、どうなっちゃうのかな〜。
 美鈴
美鈴
…………みんなも、言われてたの?
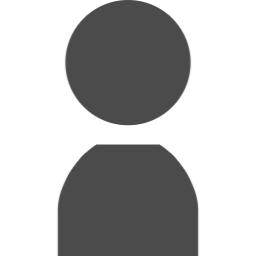 フロアスタッフ
フロアスタッフ
うん。帝塚山さんほどお客様とお話してるわけじゃないから、ちょこっとだけど。
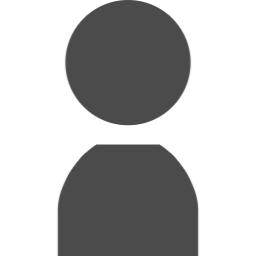 フロアスタッフ
フロアスタッフ
味はいいけど何かが足りないだとか、堅苦しいとか。そう言ってくるお客様が増えてるよね。
 美鈴
美鈴
…………。
 美鈴
美鈴
(そう……だったんだ)
ぎゅうっと、やるせない気持ちが胸を締めつけていく。
 美鈴
美鈴
(露衣さんは、本当は嫌だっただろうに折り詰めだって黙認してくれてた)
 美鈴
美鈴
(なんだかんだ言いながらも、お客様と仲良くするのだって認めてくれて……)
それに、何よりも彼の料理は美味しい。
 美鈴
美鈴
(なのに、お客様は満足できていないんだ)
 美鈴
美鈴
(それだけじゃ……ダメなんだ)
お店の経営という難しさを痛感する。
どうすることもできない自分が、ただもどかしかった。
・
・
・

レストラン店内
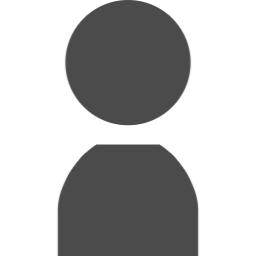 調理スタッフ
調理スタッフ
だから、言ってるじゃないですか! いい食材ばかりだけじゃなくて、価格を下げることも大事だって!
営業終了後、厨房から大声が響いて目を丸くする。

レストラン廊下
慌てて覗いてみれば、露衣さんと調理スタッフがもめていた。
 露衣
露衣
別に俺は、自分が目指すものと求めるものが違う客なら来なくてもいいと思っている。
 露衣
露衣
いい食材を使うことで最高の料理ができるし、作るからにはベストを尽くしたい。
 露衣
露衣
……それが俺の料理だ。
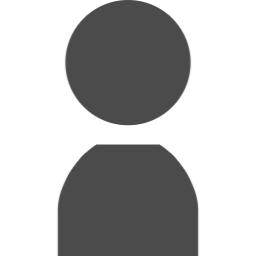 調理スタッフ
調理スタッフ
だから、それを求められてないって言ってるんすよ!
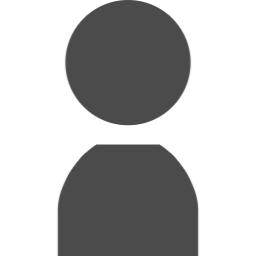 調理スタッフ
調理スタッフ
技術はあるんだから、それを安い材料で生かせばいいんだ!
 露衣
露衣
俺に技術の価値を下げろと言っているのか。
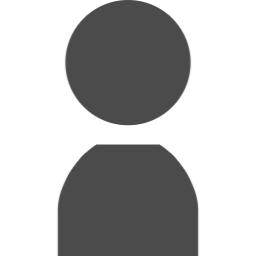 調理スタッフ
調理スタッフ
っ! ……だからっ!
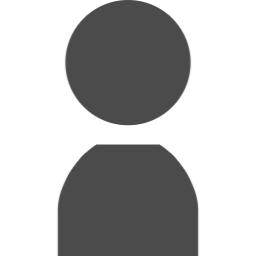 調理スタッフ
調理スタッフ
…………もう、いいです。わからないなら好きにしたらいい!
 美鈴
美鈴
あっ!
コック帽を叩きつけて、スタッフの彼は出て行ってしまう。
露衣さんは追いかけるどころか、難しい顔で手元の紙を見ていた。
 美鈴
美鈴
(もうっ!)

レストラン店内
 美鈴
美鈴
待って! 待ってください!
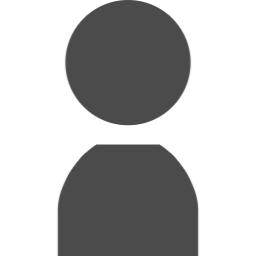 調理スタッフ
調理スタッフ
帝塚山さん……!
 美鈴
美鈴
お気持ちはわかりますけど、落ち着いてください。
 美鈴
美鈴
シェフの料理が……好きなんじゃないですか?
 美鈴
美鈴
露衣さんに憧れてここに入ったって、聞いてますよ。楽しそうに一緒に調理してる姿だって……!
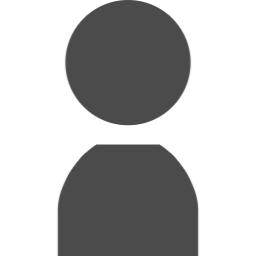 調理スタッフ
調理スタッフ
好きだけど……いや、好きだからこそ堪えられないよ。
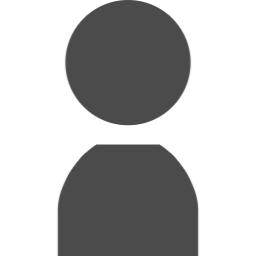 調理スタッフ
調理スタッフ
彼が変わらない限り、この店は潰れるよ。
 美鈴
美鈴
そんな……。
 美鈴
美鈴
そんなことないですっ!だってあんなに料理が——
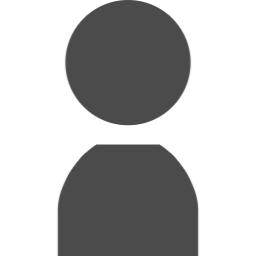 調理スタッフ
調理スタッフ
どんなに料理が美味くてもっ!
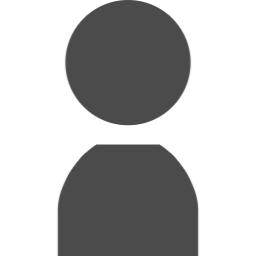 調理スタッフ
調理スタッフ
採算が取れなければ潰れる。それが現実だ。
 美鈴
美鈴
…………。
 美鈴
美鈴
(……そんな……)
・
・
・

レストラン店内
まだ誰も来ていないフロアで、俺は目の前に並べた紙を見て、息をついた。
先日、厨房スタッフがひとり辞めた。
『この店で……露衣さんのもとで、フレンチを勉強したいんです!』
——そう意気込み、元いた店を辞めてここに入ってきた者だった。
彼だけでない、俺の経営方針に賛同できないスタッフが客足が遠のくのを見て続々と辞めていく。
 露衣
露衣
(最高の料理を作りたい。……それの何が不満だって言うんだ)
 露衣
露衣
(どれも、何もかも極めている。それが……求められてないだって?)
最高のものを作っている自信はある。その味も見た目も喜ばれている自信も。
けれども、苛立つ気持ちは抑えられなかった。
ふと外を見れば、まだ始業の時間には随分と早いというのに掃除しているスタッフがいるのに気付く。
 露衣
露衣
(誰だ? こんな朝早くから)

——帝塚山 美鈴だった。
・
・
・

パラスティン邸
 美鈴
美鈴
はあ〜。昨日もひとりスタッフが辞めちゃったな。
 美鈴
美鈴
お店の空気も、なんだか最近良くないし……。
 美鈴
美鈴
お客様も増えていく気配もないしねー……。
どんどん気持ちが落ちていく。
 美鈴
美鈴
(初めてこの店に来たとき……こんなに美味しい料理を食べたのは久しぶりって思った)
 美鈴
美鈴
(ケーキも……口の中に広がるたび嬉しい気持ちになって……)
思わず掃除の手が止まる。
坂を見上げれば、青々と生い茂る山が眩しかった。
 美鈴
美鈴
(この景色も、外国にいるみたいなお洒落な店内だって大好きで……)
それに——
 美鈴
美鈴
(……露衣さんのことだって、嫌いじゃない)
 美鈴
美鈴
(頑張って欲しい、そう思ってるのに)
 露衣
露衣
おい!
思い浮かべていた人物に呼ばれて、肩が跳ねる。
振り向けば、露衣さんが立っていた。
 露衣
露衣
なんだ、今日は随分早く来てるんだな。
 美鈴
美鈴
あ……。
 美鈴
美鈴
えーと、その、ちょっと早く来て掃除しときたいな〜なんて思いまして。
その答えに、彼は察したらしく薄く笑う。
 露衣
露衣
…………ああ。
 露衣
露衣
人が多く辞めたからな。ひとりの負担が増えて、いつもの時間だと間に合わないのか。
 美鈴
美鈴
うっ……。まあ、平たく言えば……。
 美鈴
美鈴
(せっかく気を遣ったのに、何てストレートな……)
困惑する私を見て、露衣さんはふっと吐息をこぼした。
その顔は、思いのほか穏やかな表情だった。
 露衣
露衣
……悪いな。まあそれでもまだ時間があるだろう。
 露衣
露衣
お前もコーヒーでも飲むか?

レストラン店内
招き入れられて、店に入れば露衣さんは厨房へ向かう。
彼が座っていただろう席には、いくつかのノートと何枚も重ねられた紙が置いてあった。
 美鈴
美鈴
これ、先日露衣さんが見ていたヤツ? こんなに乱雑に置いて……落ちちゃいそうですよ。
直そうと手を伸ばせば、触れる前に紙は落ちてしまう。
 美鈴
美鈴
あー。もう、やっぱり。
 美鈴
美鈴
仕方ないなー。
散らばった紙に手を伸ばす。
それをまとめる途中で……私は息を呑んだ。
 露衣
露衣
こら。
 露衣
露衣
人の物を勝手に見てはいけない、そう親から教わらなかったのか。
 美鈴
美鈴
…………。
コーヒーの匂いと共に彼が帰ってくる。
上手く返事ができないのは、彼に怒られたからじゃない。
目の前に並んだ紙に、心が震えていたから。
 美鈴
美鈴
これ……! レシピ!
 美鈴
美鈴
露衣さん、新しいメニュー考えてたんじゃないですか!
 美鈴
美鈴
どうしてみんなに隠してたんですか!
 露衣
露衣
別に隠していたわけじゃない。言わなかっただけだ。
 美鈴
美鈴
ああっ、もうっ! そういうツッコミを入れたくなる返事は結構です!
 美鈴
美鈴
新メニューがあるって言えば、辞めたみんなだって考え直したかもしれないのに……。
 露衣
露衣
言わなかったのは、新しいメニューを考えても食材を改める気になれなかったからだ。
 露衣
露衣
みんなは安くて気安く来れるメニューを期待しているんだろう?
 露衣
露衣
それに応えられないのに、おいそれと言えることじゃない。
 美鈴
美鈴
露衣さん……。
 美鈴
美鈴
(譲れないんだ。どうしても、そこは)
 美鈴
美鈴
(露衣さんにとって、料理はそういうものなんだ)
まっすぐな人——
自分に対しても、料理に対しても、……みんなに、対しても。
 美鈴
美鈴
(だけど、私だってわかった)
 美鈴
美鈴
(どうしても譲れないってことが)
私の分のコーヒーを置いてくれる彼に、一歩近づく。
覚悟を決めて、向き合った。
 美鈴
美鈴
食材を……どうしても変えられないのなら、それでもいいと思います。
 美鈴
美鈴
ここは露衣さんのお店だし、それが露衣さんが求める料理なら。
 露衣
露衣
…………。ふうん。
 露衣
露衣
だから、お前も辞めるって?
 美鈴
美鈴
……いいえ。
怪訝な顔をする彼に、ハッキリと告げる。
 美鈴
美鈴
私はこの店でずっと働きたい!
 美鈴
美鈴
ずっとずっと働きたいって思ってます。
露衣さんの目が驚きに見開く。
これが私の譲れない、正直な気持ちだった。
 美鈴
美鈴
……私、この店が好きです。露衣さんの料理も。
 美鈴
美鈴
確かに値段は高いけど、貴方の技術にはそれだけの価値があるんだと思うから。
 美鈴
美鈴
だから無くなってなんか欲しくない。
 美鈴
美鈴
……こんなにも美味しい料理が、人に食べてもらう機会が無くなるなんて嫌です。
 美鈴
美鈴
私も手伝いますから、頑張っていきましょうよ、露衣さん!
思いっきり肩を叩けば、露衣さんはあっけに取られた表情をしている。
さすがにやり過ぎたかなと思ったけれど、露衣さんは笑った。
心底、面白そうに笑っていた。
 露衣
露衣
あはは。やっぱり変な奴だな、お前。
 露衣
露衣
辞めたい、辞めたい、みんなが言う中でひとりだけ辞めたくないなんて。
 露衣
露衣
本音を言えば、お前が一番に辞めるって言い出すと思ってたんだけどな。
 美鈴
美鈴
露衣さん……。
 露衣
露衣
……露衣でいい。
 美鈴
美鈴
え……?
 露衣
露衣
露衣でいい。美鈴。
 露衣
露衣
手伝ってくれるんだろう? これからも、よろしくな。

そう言って椅子に座って首をかしげる彼を見ながら淡く胸が跳ねた。
呼び捨てにされたからだけじゃない、優しげに細められた瞳に。
不覚にもこんな砕けた空気が嬉しいと思ってしまったのだ。
 美鈴
美鈴
(こ、これは! 気持ちがわかってもらえたのが嬉しいだけ! それだけ……の、はず)
 露衣
露衣
それで?お前はどうするのがいいと思う?
 美鈴
美鈴
えっ!? ええっと。
ちらっとテーブルを見れば、殴り書きをしたようなレシピがたくさん並ぶ。
どれだけ彼が根を詰めてメニューを考えていたのかよくわかる光景だった。
 美鈴
美鈴
(余計なお世話かな……)
 美鈴
美鈴
(だけど、大事なことだよね)
ドキドキしながら口を開く。
 美鈴
美鈴
露衣さ……ううん、露衣。根を詰めてる時は、息を抜くことも必要じゃない?
うん? と首を傾げる彼に、
「どこかに出かけようよ。2人で」
——そう、私は提案していた。